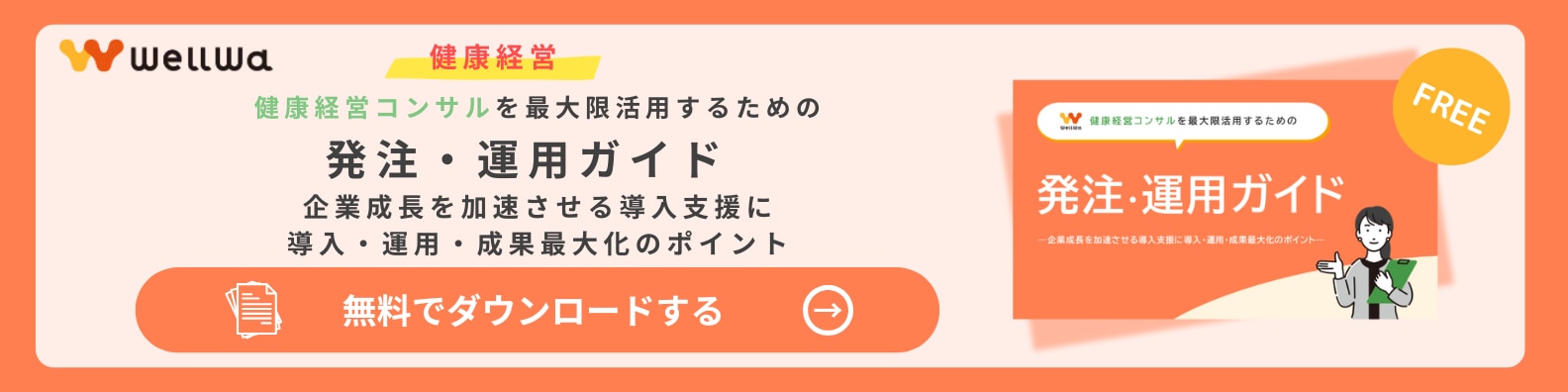福利厚生を強化する!企業が活用できる補助金・助成金制度ガイド
福利厚生の充実は、従業員満足度の向上だけでなく、企業の人材確保や生産性向上にも直結する重要な施策です。本記事では、企業が福利厚生を拡充する際に活用できる主な補助金・助成金制度について解説します。
目次[非表示]
- 1.福利厚生強化と助成金活用のメリット
- 2.活用できる補助金・助成金の種類
- 2.1.1健康支援関連の補助金
- 2.2.2働き方改革・ワークライフバランス支援
- 2.3.3人材育成・教育支援
- 2.4.4育児・介護支援
- 3.補助金・助成金の申請方法
- 4.まとめ
福利厚生強化と助成金活用のメリット
福利厚生は、給与以外の報酬として従業員の生活や働きやすさを支える制度です。近年では人材の定着や採用競争力の強化を目的に、福利厚生を見直す企業が増加しています。従業員にとっては健康維持や生活支援が受けられ、企業にとっても離職率の低下や生産性向上といった効果が期待できます。
しかし、福利厚生を充実させるには費用がかかるのも事実です。そこで注目したいのが、国や自治体が提供する補助金・助成金制度の活用です。一定の条件を満たせば、健康支援、働き方改革、人材育成など、さまざまな取り組みに対して補助を受けられます。これにより企業の費用負担を抑えつつ、福利厚生を効率的に拡充することが可能になります。
活用できる補助金・助成金の種類
1健康支援関連の補助金
健康診断・人間ドック補助
多くの健康保険組合では、人間ドックや法定外の健康診断を受診する従業員に対して、一定額の補助金を支給しています。また、一部の自治体でも事業者向けに健康診断の助成制度を設けており、従業員の健康管理を支援しやすくなっています。特に中小企業にとっては、これらの制度を活用することで福利厚生の充実とコスト削減の両立が可能です。
メンタルヘルス対策の助成金
2025年度現在、ストレスチェックそのものを対象とした単独の国の助成金制度は存在しません。ただし、代替制度として「団体経由産業保健活動推進助成金」(厚生労働省)があります。
この制度は産業医の意見聴取や保健指導、職場環境改善支援など包括的な産業保健活動を支援する助成金で、ストレスチェック結果を踏まえた職場環境改善活動も対象に含まれています。申請は産業保健総合支援センター等の団体を経由して行う仕組みに変更されており、企業単独で直接申請する形ではなくなっている点に注意が必要です。
2働き方改革・ワークライフバランス支援
働き方改革推進支援助成金
時間外労働等改善助成金(労働時間上限設定コース)は、時間外労働削減に取り組む中小企業に対し上限200万円(週休二日制導入で加算あり)を助成する制度です。従業員の健康保持と業務効率化の両立を目指す企業に適した制度です。
テレワーク導入支援補助金
テレワーク環境を整備する企業に対して、IT機器の導入費用やネットワーク構築費用を補助する制度が国や自治体から提供されています。コロナ禍以降、テレワーク導入が進んだことから、引き続き支援が強化されています。これにより従業員の柔軟な働き方を推進し、育児・介護との両立も実現しやすくなります。
3人材育成・教育支援
キャリアアップ助成金
非正規雇用の従業員に対して、企業がスキルアップの機会を提供することを支援する制度です。職業訓練やOJTの実施にかかる費用が対象となり、一定の訓練時間を満たすことで助成が受けられます。従業員のキャリア形成を支援することで、企業全体の生産性向上にもつながります。
教育訓練給付制度の活用促進
厚生労働省が管轄する教育訓練給付金は、従業員が自らスキルアップのために行う資格取得や講座受講に対して、国が費用の一部を負担する仕組みです。対象となる講座は多数あり、ビジネススキルから専門技術、介護・福祉関連の資格まで幅広く対応しています。企業としてこの制度の利用を推奨することで、従業員の自己啓発を支援できます。
4育児・介護支援
両立支援等助成金
育児や介護を理由に一時的に職場を離れる従業員に対して、職場復帰支援を行う企業が対象となる助成制度です。育児休業を取得した従業員が職場に円滑に復帰できるよう、計画的な支援体制や職場環境の整備を行った企業に助成金が支給されます。これにより、従業員が安心してライフイベントに対応できる職場環境を構築できます。
企業主導型保育事業補助金
内閣府が推進する企業主導型保育事業は、企業が設置する保育施設に対して補助金を提供する制度です。従業員の子育て支援を目的としており、施設の整備費や運営費に対して支援が受けられます。働く親を支援する企業イメージの向上につながるほか、優秀な人材の確保や定着にも効果を発揮します。
補助金・助成金の申請方法
申請前の確認事項
補助金・助成金を申請する前に、以下の点を確認しておくことが重要です。
- 最新の情報の確認:制度は年度ごとに変更される可能性があるため、最新の情報を確認する
- 申請条件の精査:企業規模や業種、取り組み内容など、条件を満たしているか確認する
- 申請期間の把握:多くの制度には申請期間が設けられており、計画的な準備が必要
申請の進め方
- 担当窓口への相談:まずは管轄する機関や団体の窓口に相談し、適切な制度を紹介してもらう
- 必要書類の準備:事業計画書や見積書など、申請に必要な書類を準備する
- 審査と交付決定:審査を経て交付決定を受けた後、計画に基づく取り組みを実施する
- 実績報告:取り組み完了後、実績報告書を提出して補助金を受け取る
効果的な活用のコツ
- 複数の制度の組み合わせ:相互に排除されない限り、複数の制度を組み合わせることも可能
- 専門家への相談:社会保険労務士や中小企業診断士など、専門家のアドバイスを受けることで申請の成功率が高まる
- 計画的な取り組み:単年度だけでなく、中長期的な視点で福利厚生の拡充計画を立てる
まとめ
福利厚生の拡充にはコストがかかりますが、各種補助金・助成金を活用することでその負担を軽減できます。特に中小企業にとっては、制度を上手に活用することで従業員サービスを充実させつつ、健全な経営が可能になります。
健康支援・働き方改革・人材育成、育児・介護支援など、企業の課題や方針に応じて適切な制度を選び、活用することが成功の鍵となります。
福利厚生の見直しを検討する際は、まず自社が活用できる補助制度の有無を確認し、従業員満足度の向上と経費削減の両立を目指しましょう。